| 前 | 1987年 6月 |
次 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
>^))<'s Diary

















































2002-06-04(火)
_ ワールドカップ日本戦
日本対ベルギー戦。大賑わい。会社なんか「テレビ観るから早く帰るよ〜(^-^)」っていう方が,正しいと思う。
でも事務所の最終当番して帰った。
2005-06-04(土)
_ なんか不調
(x_x)吐き気,頭痛。昼からの英語教室休んでしまいました。
ダメだ〜。。。寝てた。o(+_+)o
_ コンサート
このところ毎週のように行ってるような。。
でも今日は超ビック。。始めてお腹さすりながら行ってきた。
ユーミンコンサート@大阪フェスティバルホール。
(@^-^@)と家から二人で自転車で。

プッチーご夫婦と会場で合流。
- 恋の苦さとため息と
- 太陽の逃亡者
- Choco-language
- Walk on,Walk on by
- 瞳はダイアモンド
- 冷たい雨
- 雨の街を
- 静かなまぼろし
- 灯りをさがして
- 罪と罰
- あの日にかえりたい
- Valentine's RADIO
- チャイニーズ・スープ
- 別れのビギン
- 水槽のJellyfish
- DOWNTOWN BOY
- 青春のリグレット
- ついてゆくわ
- やさしさに包まれたなら
- Invisible Strings
アンコール
- コバルト・アワー
- さざ波〜ダイアモンドダストが消えぬまに〜星空の誘惑〜真珠のピアス〜DANG DANG〜埠頭を渡る風
- DESTINY
モアアンコール
- 青いエアメイル
モアモアアンコール
- 卒業写真
_ 素晴らしいステージ&パワフル。
「Down town boy」「青春のリグレット」「卒業写真」は知ってたけど,他は圧倒的に知らんかった。
「Down town boy」「青春の〜」二曲はコンサート終盤の大盛り上がりの曲だとわかった。
「やさしさ・・」は魔女の宅急便の曲だ。(=^・^=)ゞ
いつもの角氏とはかなり違う。(@^-^@)によると,こういうのがステージというらしい。角氏のは音楽隊らしい(--;;。。
以下気づいたことを忘れないうちに書いとこう。
- ユーミンがとてもパワフル!(51歳に見えない)
- 曲に併せて手品が出てきた。(@^-^@)に言わせるとMr.マリックに特訓を受けたらしい。
- ユーミンのステージに占める面積の割合がでかい。舞台セットが何回も変わる。(角氏の場合は最初からずっと同じ。1回でも変わると客はどよめく)
- ユーミンの衣装が何度も変わる。
- 譜面がない。(角氏は1曲終わるごとに「はい。えーっと次は。。。」と譜面めくりで始まる)
- バンドは全員黒子なんだけどステージ効果に貢献してる。衣装が揃ってる。全員ワイヤレスですっきり。(角バンドはメンバーの衣装特に統一感なし(^^;;)
- 間奏はあるけどソロがない(角氏の場合,全員でソロをグルグル回しする。。)
- 管楽器なし。ステージに意味のある小物が多数。
- ドライアイスが出てくる(普段実験で高圧ガスをよく扱うので妙に気になる。まぁ1ステージ,液体で200kgは使ってるかなぁ。)
- (@^-^@)が ホモカップルたくさん見つける!
_ 休憩
DOJIMA cafeにて。


2009-06-04(木)
_ 小野田のホテル

ホテルのあさごはん。久しぶりに洋食バージョン。
_ 小野田駅(朝)


いつも高校生の通学時間と一緒になって2両編成の電車は満員。
_ 訪問先で実験
_ 今日も小野田ホテル
会社の共用Let'sNoteを持ってきたが,Adobe Reader6とか古いので,更新。
_ ばんごはん
コンビニで調達。明日もあるし早く寝た。
2015-06-04(木)
_ 晩
_ ガラス発祥の地
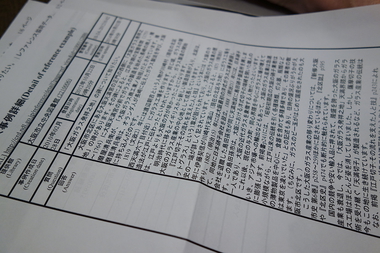
いろいろ調べたら興味深いことがたくさん!
江戸中期(1751~1764)に大阪天満宮の前でガラスの製造を始めた
長崎の商人・播磨屋清兵衛(はりまや-せいべえ)が大阪の天満宮前に工房をひらいた。
播磨屋清兵衛は、オランダ人が長崎に伝えたガラス製法を学び、大阪に持ち込みました。
1819年には渡辺朝吉という人物が川崎村にガラス工場を作りました。
同じ頃、ガラスの製造法が江戸に伝わったといわれていて
ガラス製造の開始は、江戸よりも大阪の方が早かったことになるようです。
『江戸切子:その流れを支えた人と技』という本には「大阪のカットグラス」という1章が設けられており、
大阪のガラス産業の歴史の一端が詳しく記されています。
それによると、1875(明治8)年に伊藤契信が川崎村天満山(現在の北区与力町)に
ガラス工場を作り、
1882(明治15)年には大阪最初の洋式ガラス工場を新設して、同地に日本硝子会社を設立。
1888(明治21)年には、日本硝子会社を退職した島田孫市が同じ天満地区に
島田硝子製造所を興します。
この島田孫市は、大阪における洋式切子の端緒を開いた職人の一人であり、
大阪の近代ガラスを象徴する人物だったといいます。
またこの地に 象印の本社があるのも魔法瓶もガラスからできていて
創業者はこのあたりの電球職人だったそうです。
日本最大のガラス商社のカメイガラス。
学者肌だった社長が薩摩切子のよさを忠実に復刻して、商品化を実現ました。
その後、カメイガラスは倒産しちゃったけれども、カメイガラスがなかったら
薩摩切子は今みたいに有名にはなっていなかっただろうし、その流れから、
現在では天満切子も生まれています。
_ BGM
- Instrumental II / James Taylor
- Don't Let Me Be Lonely Tonight / James Taylor
- Lio De Janeiro Blue / Nicolette Larson
- タラのちゃんのテーマ1
2016-06-04(土) 近畿地方 梅雨入り宣言があった
_ 今日は 三つ星会
_ 待ち合わせに ラピートで
_ 堺駅 到着
_ ランチ
_ さかい利晶の杜
1階は 千利休の展示
2階は 与謝野晶子




『市中の山居』しちゅうのさんきょ(都会にいながらにして山里の風情を味わう)
引き算の美学
_ 駿河屋の三女 与謝野晶子
_ かん袋




お餅をくるんで食べるところから「くるみ餅」
くるみのお餅ではない(笑)
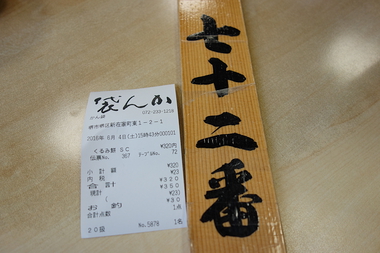

かん袋は、鎌倉時代末期、1329年に和泉屋徳兵衛が
和泉屋という商号で御餅司の店を開いたのが始まり
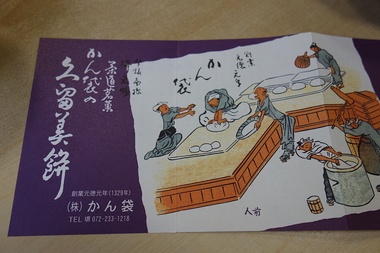
_ 有名らしい
_ ことりっぷ♪
_ 堺伝統産業会館
_ つぼ市製茶本舗
_ 阪堺電車で恵美須町まで乗って帰る
_ ただいまー
_ 晩
_ >^))彡 らんち
2017-06-04(日)
_ AM4時 起床
_ 湯めぐり
_ ステラテラス
_ 朝食
_ レンタサイクル
_ 洲本城で待ち合わせ
_ ランチ いたりあ亭
_ 15:00発 阪急バス
_ ただいまー
_ 今日は日の出から日の入りまで(笑)
_ チケット届いたー♪















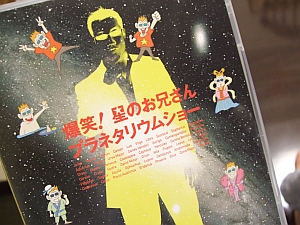




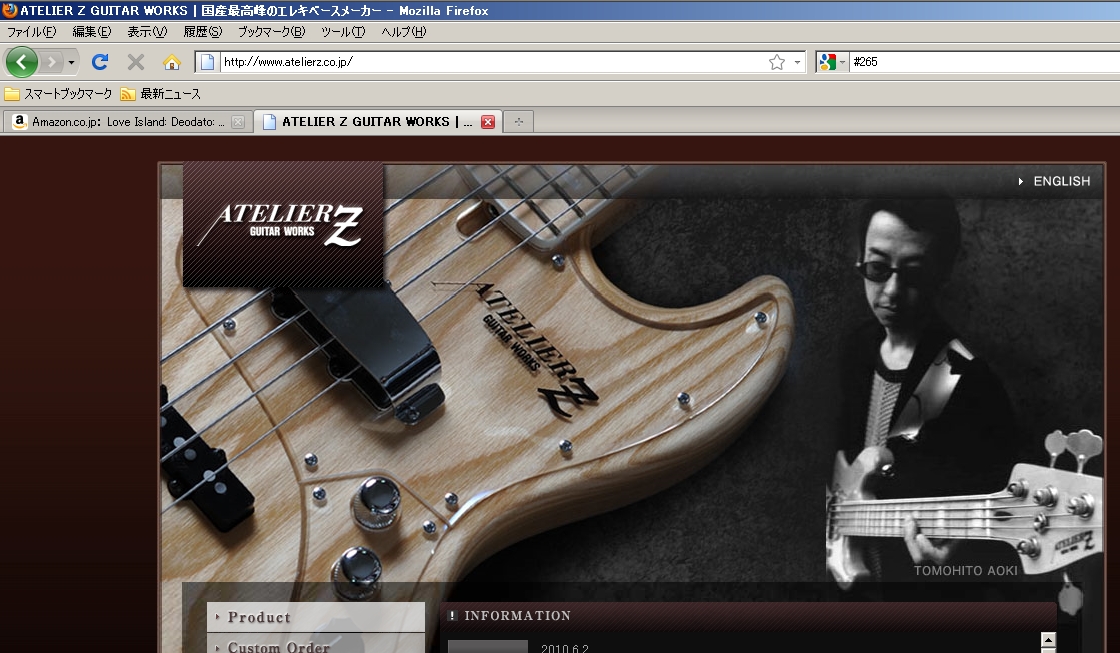






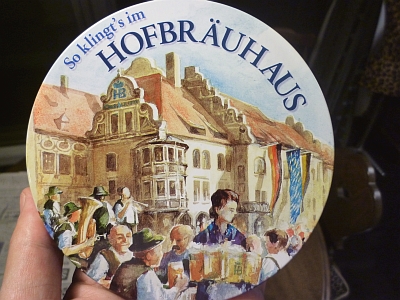

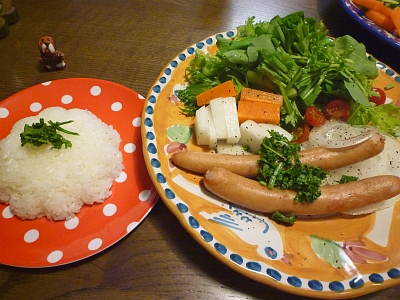









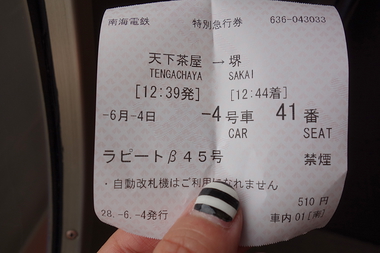





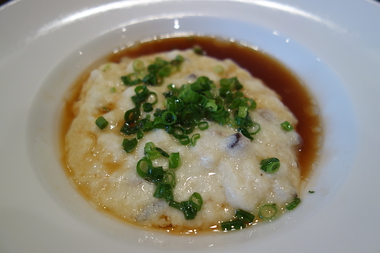






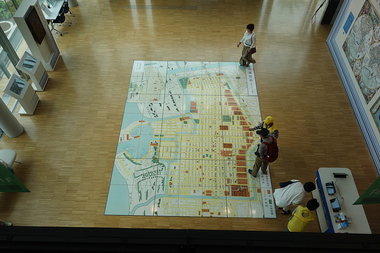















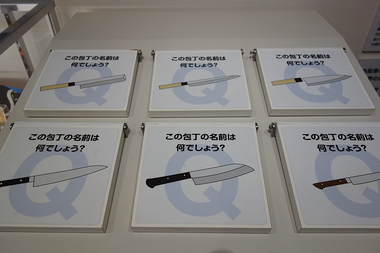

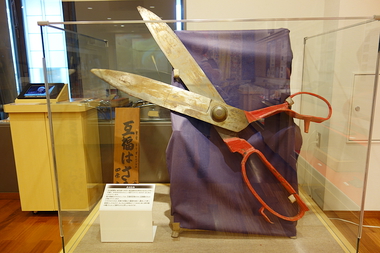



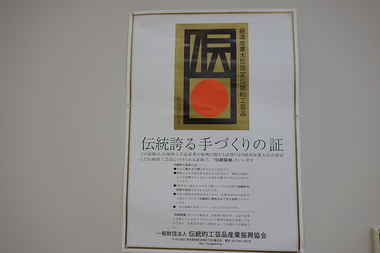









































































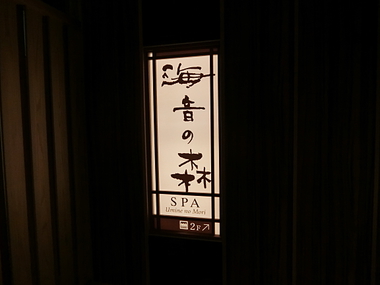































































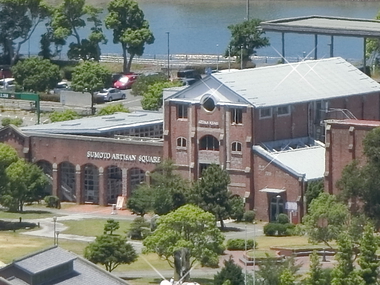




































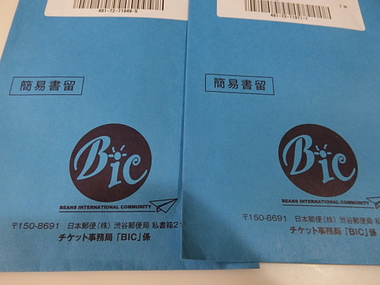
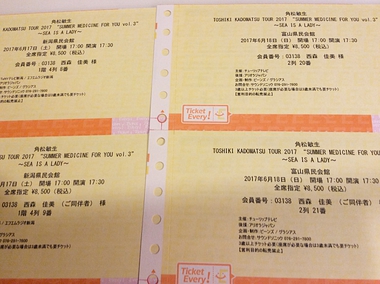










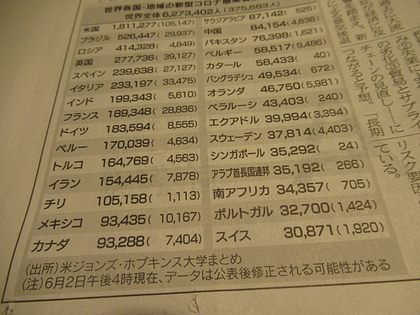













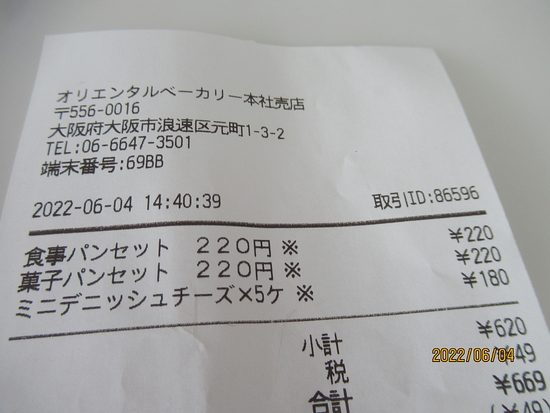




















































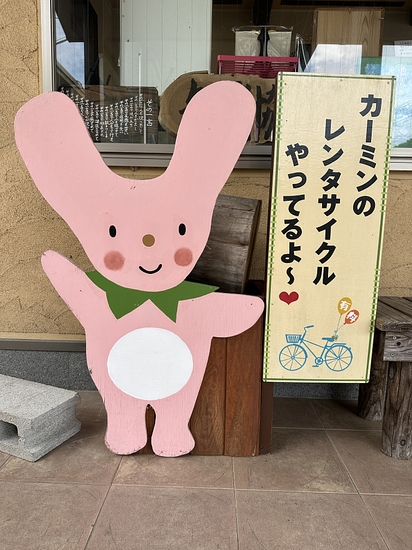






















































































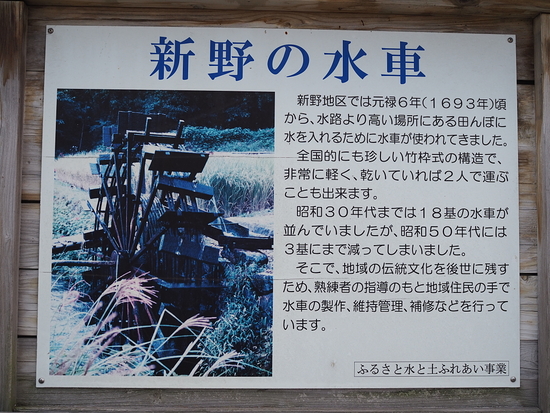





















































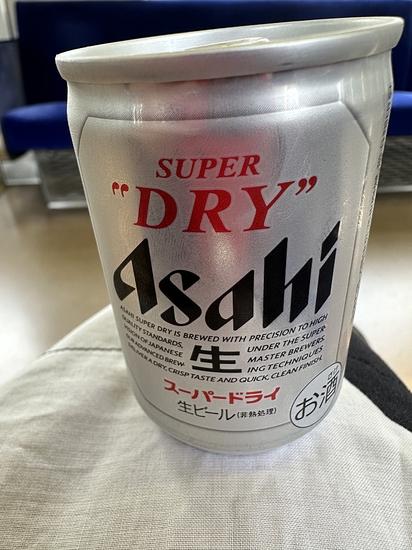





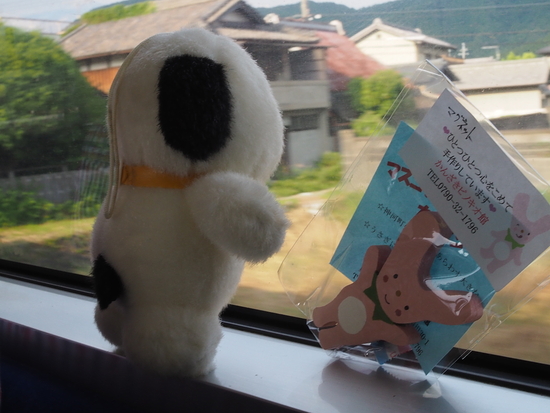
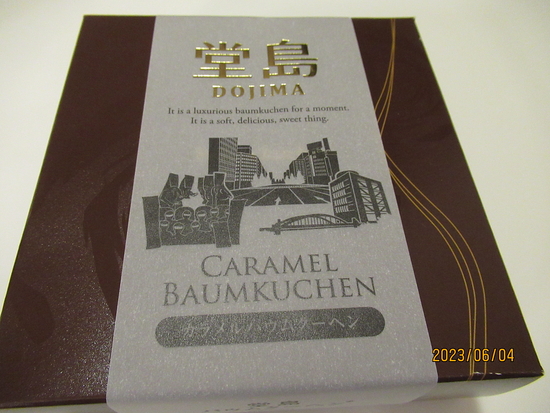


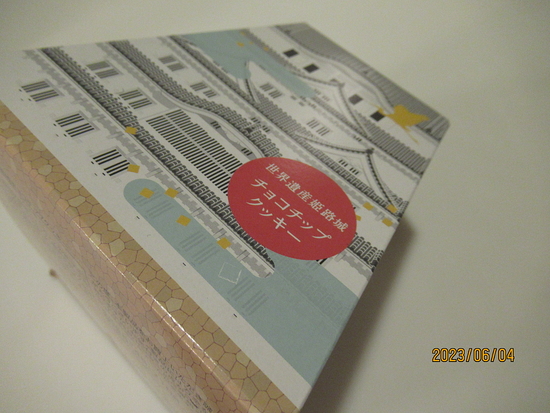

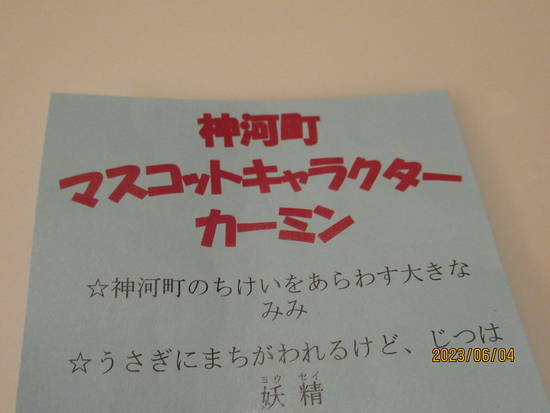













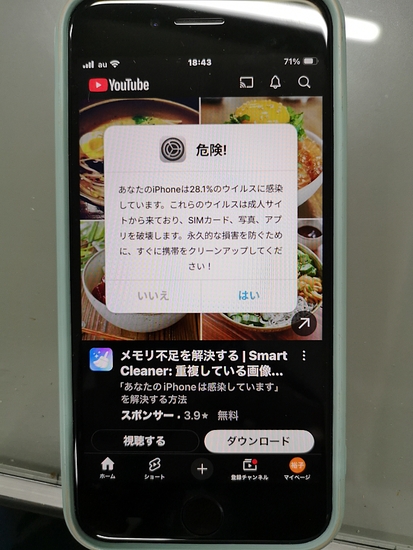



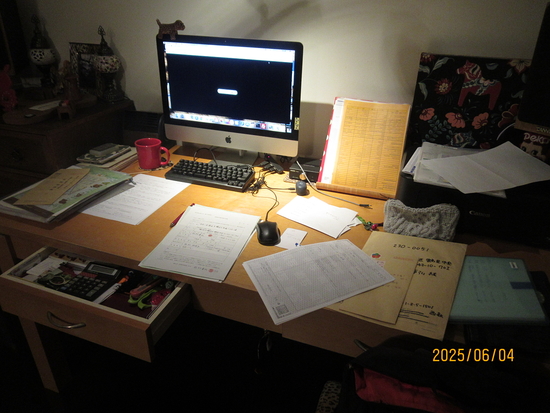
_ ま [角と比べんといてえ。しくしく。]
_ ま [新PC全快だす。 うれしくって何度もツッコんでしまうわ。]